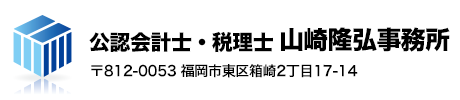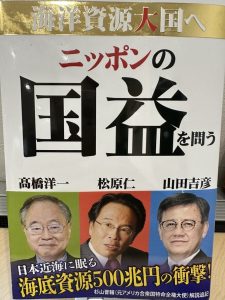 書評
書評「第一部 海洋資源大国ニッポンの国益」として衆議院の松原仁議員、「第二部 海洋資源立国への道筋」として技術、予算、国際環境の面から東海大学海洋学部の山田吉彦教授、「第三部 国益の実現と海洋資源大国への財政」として元財務省官僚の高橋洋一さんが分担しての著作です。
海洋資源開発の全ての活動は、1994年発効の「国連海洋法条約」の枠組みの中で行われます。このなかには排他的経済水域(EEZ)における主権的権利が認められており、日本が有する世界第6位のEEZ(約447平方㎞)は、日本の海の領土とも言える広大な資源ポテンシャル域となっています。
なんと、日本の海底にはメタンハイドレート、レアアース(希土類)泥、コバルトリッチクラフト、海底熱水鉱床など、ハイテク産業やエネルギー供給の鍵となる可能性を秘めた多様な資源が眠っていることが、近年の調査により明らかになってきています。メタンハイドレートだけでも日本の天然ガス消費量の100年分以上、レアアースは世界需要の数百年分とも言われるほど莫大だそうです。これらの資源を商業的に開発・利用することができれば、経済的便益は500兆円規模に達する可能出があるとのことです。
しかし、山田教授の試算では、本格的な商業生産に至るまで、100兆円規模といった巨額の初期投資が必要とされます。国の借金は1,200兆円を超えているのに、巨額の投資など出来ないという悲観論に対して、高橋洋一さんは統合バランスシート、企業会計でいえば連結決算で考えるべきと提言します。政府と日本銀行を連結すれば、政府の発行国債は日銀の保有国債と相殺され、差し引き純資産は700兆円のプラスとなります。統合バランスシートの視点こそ「海洋資源大国」への道を切り拓くための財政的な裏付けとなります。
結論として、豊かな社会を次世代に引き継いでいくために、第一のエンジンである「海洋資源大国」と、第二のエンジンである「AI立国」の二つが総合に補完し合い、強力な相乗効果を生み出すとしています。久々に夢のある話でした。